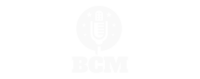ビットコインが誕生して10年が経ちました。暗号資産(いわゆる仮想通貨。以降、暗号資産で統一します)が通貨とみなせるのか様々な議論もあり、より本質的にそもそも通貨とは何なのか?といったことを私自身も考えることが多くなりました。
私はビットコインを始めとするいくつかの暗号資産は、「お金」として利用できると思っており、その背景を今後コラムでも配信していく予定です。そこでは「お金」の本質について、一般的な定義を超えた議論したいと考えております。また最近では、FacebookがLibraという暗号資産を来年発行する、と発表がありました。SDRのように複数の法廷通貨のバスケットに連動した通貨のようです。通貨を考える上でも、ぜひ今後のコラムの題材にしたいと思います。
暗号資産の特徴と法定通貨への誤解
さて、暗号資産には様々なユニークな特徴がありますが、通貨という観点では、中央銀行あるいは政府といった明確な発行体が存在しないこと、が大きな特徴の1つになるでしょう。発行体があるのがなぜ重要と考えられるのか、その深い議論はいったん置いておくとして、発行体の存在やその信用が当たり前になると、利用者の間でも「発行体がその通貨の保証をしてくれている」、「誰かが発行しているほうが安心」といったことが通貨の必要なことである、と思われるかと思います。
今日のほとんどの法定通貨は、実は国家含めて誰も通貨の価値を保証していないのですが、そういった保証がされているから安心して利用できるという、あえて言いますが、「誤解」が半ば当然化されています。
一方、昔の貨幣制度はどうだったのでしょうか。特に「中央銀行」と呼ばれるような、現在に通じる貨幣制度が出来上がる前は、どういった制度だったのでしょうか。
渡来銭(とらいせん)
ここ日本において、平安時代末期から戦国時代くらいまで使用されていた貨幣は、主に渡来銭(とらいせん)と呼ばれる中国から輸入された銅銭でした。日本で本格的に貨幣の使用が始まったのは、平安時代末期の平清盛の時代と言われています。平清盛が中国から銅銭を大量に輸入し、それらを経済活動に使うことを半ば強制したのが始まりとも言われているようです。以降、中国からの輸入される銅銭、渡来銭が日本における貨幣の中心となりました。

この渡来銭で代表的なものは宋銭で、時の中国の王朝である宋が発行した通貨となります。
渡来銭はおよそ400年間にわたり利用されてきましたが、興味深いのは例えば宋(960-1276)が滅んだ後の時代においても、日本では宋銭は当たり前のように使われていたことです。
現代の我々には、すでに存在しない他国が発行した通貨を利用する、というのは想像しづらいことですが、一般的にいわれるような「発行体(≒国)が存在し、その信用によって価値が保証、あるいは決定されていることが通貨には不可欠」というようなことを真っ向から否定するような状態が成立していたと考えられます。
コンセンサスが生み出す通貨への信用
このような通貨の利用の仕方は、ビットコインにおけるそれと似ていると思いませんか?
確かに渡来銭は、かつてそれを発行した国家は存在していますが、発行体があることの大きな意味である、「その発行体に対する社会的信用」という観点では、宋が滅んでいる時点で実質的に失われております。
またそもそも、渡来銭を使っていたとはいえ中国の経済に組み込まれていたわけでもなく、中国の時の王朝の信用を基準として日本で使用されていたわけでは全くなかったようです。例えば、日本で流通した渡来銭は特定の銅銭のみで、中国では大型貨幣であった銅銭もわざわざ(中国での価値を失わせるような)加工して小さな銅銭として使用したり、中国で紙幣に移行している時代においてもその紙幣は全く日本では流通しませんでした(出展:東野治之「貨幣の日本史」)。
このように当時の日本人は、その銅銭の発行体に依存した経済でもなければその貨幣を使用する義務を国家から強制されていたわけでもありませんでしたが、そういった銅銭を経済活動に使用しておりました。

現代の感覚からは驚くべきことにように感じますが、渡来銭という、人々のコンセンサスによって決済手段として成り立っていたものを、日本では400年近く使用されており、これは日本銀行が出来てから150年も経過していないことを考えると、むしろ歴史的には日本ではより馴染みのある制度でもあります。当時の人たちが理解できるかどうかはともかく、ビットコインが取引可能な形で存在したとすれば、使用されていた余地は十分にあるのではないでしょうか。
ちなみに、金や銀と異なり、銅自体は珍しい金属ではありません。宋銭は最盛期には年間60億枚と大量に生産されており、その数の多さから現在でも宋銭の価値は骨董的価値含めてほぼありません。よって銅銭そのものの金属としての希少性に裏打ちして使用されていたわけではないと考えられます。
中世ヨーロッパのプライベートマネー
また中世ヨーロッパにおいても、貨幣鋳造権は支配する王朝に属しておりましたが、王朝の財政に応じて貨幣は鋳造されるため、そういった「信用できない」通貨による支配から逃れるために、大商人の間で私的な決済ネットワークが誕生し、同時にプライベートマネーが当然のように使われるようになりました。為替手形や銀行という「技術」が、こういったプライベートマネー、私的決済ネットワークから誕生することになります。そして、このプライベートマネーに足りなかった「権威」を国家からお墨付きをもらってできたのがイングランド銀行、現代の中央銀行制度の幕開けとなります。

つまり、現代の中央銀行はそもそも「国家」が発行している通貨ではなく、経緯からいえば民間が発行するプライベートマネーの延長線上にあるものです。実はこのことは、「中央銀行の独立性」という定義上当たり前のことでもあるのですが、改めてその経緯を考えてみると発行体(≒国家)ありきの現代のイメージとは、通貨の本質は異なることが理解できるかと思います。
まとめ
「国やあるいはそれに準じる(信用できる)発行体がいる」ことが通貨の条件あるいは貨幣制度の大前提、という考えに対して、歴史的にはそうでもない例をここでは紹介しました。これはFacebookの暗号資産Libraを考える上でも参考になります。
ただ、「中央銀行が誕生する以前の例を言われても、そこから進化してできたのが中央銀行じゃないの?結局は大衆が、発行体がいてその信用を国家と結び付けてイメージするから通貨としてこれまで成立しているのでは?そこから戻れないでしょ?」というご意見もあるかと思います。そこで第2回では、時間を現在まで飛ばし、通貨が何かを考える別の興味深い例をご紹介したいと思います。
なお、本コラムを読み「通貨の価値」についてご興味を持った方は、ぜひ私が2019年5月に執筆したレポートをご覧下さい。今後コラムでも触れていきたいと思います。
現代において通貨が使用できなくなると何が起きるのでしょうか。大規模な経済混乱や貧困、プライベートマネーや暗号資産への逃避や利用などがイメージしやすいかと思います。
しかし一方で、経済混乱が生じずにむしろGDP成長を成し遂げた事例もあります。そこから読み解れる通貨の本質の1つ、そして繋がっていく信用創造の世界に第2回コラムでは触れる予定です。