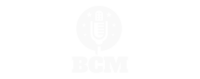- 上場企業アステリアが議決権システムにブロックチェーンを採用
- アステリア株式会社は世界初、株主総会における議決権投票システムにてブロックチェーン技術を適用した。国内の大手企業に活用されているブロックチェーン技術の開発事例や最新動向をまとめて掲載。
上場企業、議決権システムにブロックチェーンを採用
ソフトウェア開発を手掛けるアステリア株式会社(旧:インフォテリア株式会社)(*1)は、6月22日の株主総会において三菱UFJ信託銀行の協力のもと、議決権投票システムにブロックチェーン技術を適用した投票システムを実現した。今回の株主総会では、議決権投票システムを初めて本番環境で導入した事例となる。イーサリアムブロックチェーン上に発行されたデジタルトークン(権利証)を使用することで、議決権を有する株主はネット上で議案に対する賛否をブロックチェーン上に記録するシステムを利用した。
アステリア株式会社とは
1998年に国内初のXML専業ソフトウェア会社として設立されたアステリア株式会社(2018年10月にインフォテリアから社名変更)は、企業内の多種多様なコンピューターやデバイスの間を接続するソフトウェアやサービスを開発・販売している。
今回の株主総会において議決権を有する株主9,307名は、自身の所有株式数に応じたデジタルトークンを自動的に受け取り、定時株主総会に上程される4議案、10項目に対する賛否を投票。通常のネット投票、郵送、総会への出席などと併せてブロックチェーンを利用したデジタルトークン(権利証)が利用された。上場企業の議決権システムの本番環境にブロックチェーンを採用することは、世界初の事例だ。

出典:アステリア株式会社
ブロックチェーン技術を適用した議決権投票システムの特長は以下の通りだ。
- 基盤技術として、ブロックチェーンを適用
- 実際の当社株主の所有株式数に応じた議決権(デジタルトークン)を発行
- 議案毎に複数デジタルトークンを同時に発行して集計が可能
- 票数の改ざんが株主総会主催者関係者でも物理的に不可
- 特別なアプリを必要とせず、PC、スマートフォン等から投票が可能
- 票数の改ざんが株主総会主催者関係者でも物理的に不可能
- 投票期間内は24時間いつでも投票の受付が可能
国内大手企業によるブロックチェーン開発事例
ブロックチェーンは、フィンテックの中核技術として金融業界における適用が注目されており、最近では金融業界に限らず幅広い領域で適用の検討が行われている。以下に国内におけるブロックチェーンの活用事例及び開発事例についてまとめた。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
2019年2月12日には、ブロックチェーンを活用した決済ネットワークの提供を目指し、新会社「Global Open Network株式会社」を設立すると発表。発表資料には、「決済処理速度2秒以下、世界最速の取引処理性能毎秒100万件超の取引」と具体的な性能が記されている。さらに、機能拡張により「毎秒1000万件」への展望も可能と記している。
SBIアートオークション株式会社
またSBIは今年4月にブロックチェーン技術を応用したアート作品に関する所有権の証明などの共同プロジェクトを開始。SBIアートオークション主催のセール「Modern and Contemporary Art」と連動したコンテンツを展開し、セールに出品される500点超・総額4.5億円の作品を紹介すると共に、落札者のうち希望される方にブロックチェーンの証明書を付与する。
ブロックチェーン証明書には、タイトル、サイズ、技法といった作品情報のほか、所有履歴情報や修復履歴、著名美術館やギャラリーに展示された履歴、オークションでの出品履歴など様々な情報を記録できる上、これらを第三者が改ざんすることが困難なため、アート作品の所有権や真贋の証明書が偽造されるリスクが飛躍的に低くなる。
ソニー株式会社
2018年10月15日には、ソニー株式会社はブロックチェーン技術を活用したデジタルコンテンツの権利管理システムの開発を発表。このシステムは、電子教科書やその他の教育用コンテンツ、音楽、映画、VRコンテンツ、電子書籍など、さまざまな種類のデジタルコンテンツの権利管理に役立つ。
情報の破壊や改ざんができないブロックチェーンベースの著作権管理システムを作り出すことで、①電子データの作成時期の証明、②改ざんできない事実情報の登録、③過去に登録済みの著作物との照合・判別、④データの生成日および生成者を参加者間で共有・証明することの4つを実現する。
ブロックチェーン技術は大きな社会実験
ブロックチェーン技術は、既存の社会システムに新たな可能性を生み出し、データに透明性をもたらす。今後も大手企業のブロックチェーン活用事例は増加すると考えられるが、全体として大きな社会実験中であることには留意が必要である。
当然、活用事例や開発事例には筋の良し悪しがあるが、ユーザー自身が実際に活用、フィードバックをしていくことが将来の業界発展に対するベストプラクティスと言えるのではないだろうか。